子どもが英語を読めるようになるために必要なことー理論編
以前、「英語が読めるようになるまでの道のり」という題で、娘がキンダー及び一年生を通して学校でどのように英語を読む事を習ってきたかについて書いた。今、二年生があと数ヶ月で終わるという時期だが、この一年間も前の年の一年生の時と大体同じような勉強を学校ではやってきたようだ。
宿題は単語(スペリング)の練習のようなもの(「英語が読めるようになるまでの道のりー一年生」)と同じものを続けた。それ以外にはとにかく毎日15分本を読むことが課された。本は何でも良いとの事。娘は簡単なChapter Bookとよばれる、薄い本(ペーパーバック)や、絵本を自分で読んでいた。
英文読解を学校でやると、英語の熟語というか言い回しや単語がわかっていないところがどうしてもあるので、満点にはならないが、理解力はちゃんとついてきているらしい。
DPNSのペアレント・クラスで、ある晩、娘の学校の一年生担当の先生が講師に招かれ、小さい子どもがどのように英語を読めるようになるのか、そして親はどうやってそれをサポートしたらよいのか、という話を聞く事が出来た。
彼女によると、文(英文)を読むために必要な技術・能力というものを考える際に有効な考え方に、以下のものがあるという。そもそも文を読むという作業は何をすることか。
それは文章という記号を解読(Decoding)し、理解(Comprehension)することである。
読解のために必要なのは、単語を認識できること(Word Recognition)、単語や文を見てすらすらと理解できること(Fluency)である。
そして英語の単語の認識に必要なのは、
Concepts of print
・・・文字、単語、文章が印刷してあるということが理解できる。
Phonics
・・・フォニックス、英語の文字がどういう組み合わせだとどういう発音になるかの基本を知っている。
Phonemic Awareness
・・・音素を認識できる。つまり、単語は一つ一つ違う音が組み合わさってできているものであり、一つが違うと違う意味になったりするという事がわかる。英語では、どこで単語が切れるのか、どの単語と単語が韻を踏むのか、などが分かることが音素の認識につながる。だからプレスクールや低学年では繰り返しのある本や、Nursery Rhymeが重要視される。
そして流暢さに不可欠なのが、
Sight Words
・・・英語で日常的に使われる最も基本的な200位の単語。Dolch Word Listとも呼ばれる。the, they, it, was, whyなど。必ずしもフォニックスの原則に従わないので、覚えるしかないものも多い。
Automaticity
・・・以上のことをいちいち考えずに瞬間的に処理できる能力。
であるという。
更に、文章は解読できるだけでなく、理解できなければならない。それに必要なのは、Academic Language(日常会話で使うような言語ではなく、知識を学ぶための言語。書き言葉に近い?)であり、Comprehension Strategies(理解するための戦略)であるという。
Academic Languageを獲得するために必要なのは、
Background Knowledge
・・・背景となる知識
Vocabulary
・・・語彙
であり、Comprehension Strategiesを発達させるために必要なことは、
Syntax
・・・統語論などと訳されるが、ようするに英語の文の構造がわかっていること。主語がどこにきて、後からどういう風に付け足せば文になるのか分かっているということ。
Comprehension Monitoring
・・・子どもが自分で内容を理解できているか補助してやることが必要。もしわからなくなっていたら、どこでわからなくなったのか、一緒に考えてやったりすることが必要。
Reorganizing Text
・・・一まとまりの文章の順序を入れ替えて、並べ替えさせてみる。
であるという。
でも、多分、一番大事なのは、以上のことを表にした時、一番上に来る項目があって、それは「動機」だということだろう。講師の先生も、だから楽しみながらやれるようにしなくては意味がない、と強調していた。
最近のアメリカでの小学校低学年までの英語の習得のためのカリキュラムは、多分このような理論にすべて基づいていると思う。似たようなことを書いてあるサイトはすぐに見つかる。
日本でも「フォニックス」が大事という考え方は随分英語教室などでは普及しているらしい。
アメリカのキンダーや一年生では、Decoding主体、一二年生になるとComprehension主体の英語の学習をほぼ毎日やっているような感じだろう。しかし、この傾向はせいぜいここ10年位のものだ。
こういうやり方が本当に最善なのかは疑問も多々ある。
そういうことを考えさせられるミーティングにも最近参加した。それについてはまた今度。
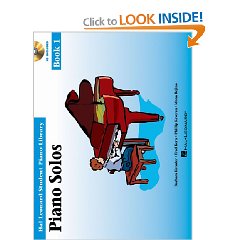
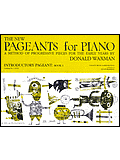
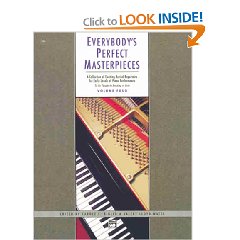
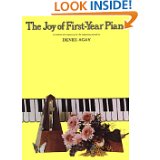
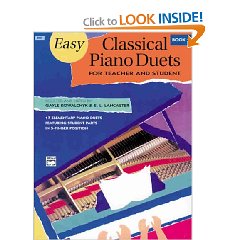
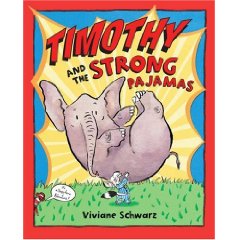
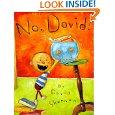
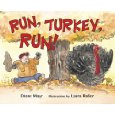
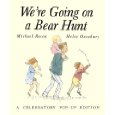
最近のコメント